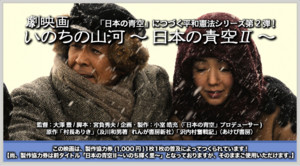この1週間を振り返って…。
この1週間も毎日が忙しく、このブログに書きたいことはいろいろとあったのですが、書き込む時間が取れなかったので、まとめて書くことにします。
1週間分の書込みですので、長文になります。
23日月曜日は既に書き込んでいるように、毎年勤労感謝の日に障がい者当事者が千波湖畔を清掃する「(知的障がい者)本人ボランティア活動」の日でした。
このような社会参加の活動を通じて、知的障がい者当事者が社会の一員として地域で生きていることを多くの市民に知ってもらうことも大切ではないかと考えます。
24日火曜日は、仕事帰りに県民文化センター小ホールで劇映画「いのちの山河〜日本の青空Ⅱ〜」の試写会があったので、参加してきました。
この試写会は、児玉正文さん(つくば市)から紹介のあった劇映画「いのちの山河〜日本の青空Ⅱ〜」でした。
いのちの山河〜日本の青空Ⅱ〜サイト
http://www.cinema-indies.co.jp/aozora2/index.php
最後のテロップに、この映画の紹介者である児玉さんの名前が製作実行委員会の一員として書かれていました。
そう言えば、映画製作強力券(試写会鑑賞券も兼ねている)を買ったときにそのようなことも言っていたなと思い出しました。
試写会に参加していた周りの顔ぶれを見ると、高齢者が多く見受けられました。
映画の内容も高齢者医療の無料化への小さな山村の首長の取り組みでもありましたので、その関係で参加者が多かったのかと思いきや試写会への招待者がほとんどでした。
制作実行委員会のメンバーからの招待者で、これから地域での上映活動に力を貸してほしいと思ってのことではないかと思います。
次回試写会は
12月3日(木)つくばカピオホール
18時30分開場 19時上映
問い合わせ先:茨城映画センター 029−226−3156
久しぶりに、良い映画を観ました。
このような映画をたくさんの方に観てほしいものです。
25日水曜日は、自閉症の娘が20歳になったので障害基礎年金の診断書を書いてもらうための「精神保健指定医の診断日」でした。
この日は、当事者の診断ですので、娘も通所施設を休んで受診しました。
この診断書を書いてもらうまでには3回の精神保健福祉士(ソーシャルワーカー)による「医療相談」がありました。
障害基礎年金裁定請求書に添付する診断書も診断した精神保健指定医(精神科医)がかなり詳細に記入する必要があります。
また別な添付資料である「病歴・就労等申立書」という書類も生まれてから現在までの状況を母子手帳や記録(誕生から就学前まで将来を想定して記録していた)に基づいて極め細やかに説明をして、3回目の医療相談のときに申立書の下書きを書きました。
それから、特別障害者手当の認定請求をするための診断書も書いてもらえるようお願いしました。
その診断書にある「日常生活能力の程度」の項目の意味も説明をしました。
診断書ができたときにはその申立書を清書して裁定請求書に添付して市年金課に持参する予定です。
精神科医(精神保健指定医)の診断では医師が直接当事者を観察すると共に、改めて誕生から現在までの状況の確認と日常生活能力の判定をしてもらいました。
両診断書にある日常生活能力の程度の違いについて詳細に説明を行いました。
併せて、特別障害者手当の診断書にある8項目のほかに、「入浴」の生活能力についても備考欄に書いてもらえるようお願いをしました。
障害基礎年金の診断書は各項目も多いので後日となりましたが、特別障害者手当の診断書はその日に書いてくれました。(内心は後日、その診断書を取りに行かなければと思っていましたが…)
次の日も別の用事のため、午前中は休暇をとっていましたので、その日に書いてくれたのは大変ありがたかったです。
ちなみに、特別障害者手当の診断書料は5,000円+消費税で5,250円でした
11月26日木曜日は、午前中に毎週土曜日に実施しているスポーツ教室の「話合い会」(年3回:学期ごとに開催)が茨城町中央公民館であったので、その前に市障害福祉課によって昨日書いてもらった診断書を添付して特別障害者手当の認定請求をしてきました。
窓口では、先日対応してくれた担当者(前回名刺を貰っていた)を名指しして、書き込んでいた認定請求書と診断書、そして所得状況申立書(所得制限を判定する資料)を提出し、受理してもらいました。
そのほかに、持参したのは本人(20歳になっているので請求人)の印鑑、銀行口座の通帳、そして療育手帳、身体障害者手帳です。
(以前に担当者から持参するものは指定されていました)
担当者は添付してある精神科医が書いた診断書の日常生活能力の程度をみて16点中、15点(「食事」は「介助があればできる」の診断になっていた)であることを確認すると、持参したもののコピーを始めました。
コピーが終わり、席の戻ってきたので、認定請求書にある「扶養義務者」というのは誰になるのかと問うたところ、請求人(本人)と生活を一にしていてその生活の主たる収入者であると説明がありました。
(この回答は想定範囲です)
それに関してインターネットなどで関係資料を確認していたので、そのつもりで総所得金額などを記入しておきました。
娘の誕生月である11月に認定請求書を受理してもらったので、認定されれば翌月(12月)から支給開始となります。
なお、障害児福祉手当(月14,380円)は20歳の誕生月まで支給されます。
併せて、特別児童扶養手当(月50,750円=保護者に支給)も誕生月まで支給されます。
その後は、スポーツ教室の「話合い会」でした。
スポーツ教室に参加している17家族中、10家族の参加でした。
平日の開催なので、仕事をしているお母さんも多いので、全員参加というわけにはいきません。
(できれば、全員参加をしてもらいほかの子どものことも含めて共通理解をして深めておきたいが…)
前回の話合い会以降の行事などの反省や意見、報告事項、そして協議事項と作成したプリントに基づき進行してもらいました。
スポーツ教室開催時には、なかなか話している時間が取れないので、このような機会に子ども達のことを含めて今後のスポーツ教室のあり方などいろいろと協議しておくことがあります。
代表である私はお昼の弁当を食べてから失礼しました。
そのあとは、いつものように各人から子どもの近況報告や困っていることなどの相談を皆さんの知恵(障がい者をもつ保護者としての経験則からの意見)を借りながら、問題解決に向けていろいろ意見を出し合ったそうです。
助言者として参加してくれたあいの家療育支援センターのサビ菅は「このスポーツ教室に参加している保護者は【ペアレント・メンター】としてもほかの保護者の助言ができる人が多い」とお褒めの言葉をいただきました。
11月28日土曜日の午後は、サンアビで「スポーツ教室」でした。
開始前に、先日のスポーツ教室での話合い会の「結果報告」のプリントが出来上がっていましたので、参加者に配布をさせてもらいいました。
昨日のスポーツ教室の参加者は当事者14人、保護者15人の総勢29人の参加でした。
これからは、冬の活動で寒さが増してくるほどに参加者は少なくなってくるかもしれません。
前半は、いつものようにいつものメニューをこなし、後半は先週と同じメニューである「縄跳び」と「タオルのボール投げ」、「タオルにボールを載せてリレー」を3組に分かれて行いました。
縄跳びといっても当事者14人中、縄跳びができるのは3人しかいません。
時間の関係もあり、十分な取り組みはできませんでしたが、このように不得意なこと、不得意な運動(自閉症や知的障がいなど障がいからくるものもあると考えています)も何回か繰り返すことによって、少しずつできることが多くなり関心が向いてくるのではないかと思っています。
「継続は力なり」と先人は言っていますが、まさにそのとおりであるとつくづく感じています。
これからも、楽しめるスポーツを多く取り入れていこうと思っています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
ご意見やご感想をいただけると嬉しいです。